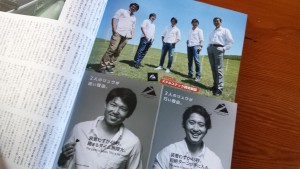今朝は此処桜川市を東西に分け雲がクッキリ別れ!
東方向は曇り、西方向は晴れ、東海沖の低気圧の影響ですね?!
そして今朝も冷え込みました!
10時前でも氷は解けず、田圃もビッチリ凍ってました!!
あした17日(土)からも続々OPEN!
近場ではたかつえスキー場が
運行リフト…第1ペアリフト、第2ペアリフト、第3ペアリフト
滑走コース…ロマンス、からまつ、パラダイス、ファミリー
営業時間…8:30~16:00
リフト料金…12月17日~22日まで 1日券 大人3,200円/小人・シニア2,200円
券売場…12月17日~18日 ロッジ前リフト券売り場、第1ペアリフト乗り場券売所
12月17日~23日のお得情報
カレーライス定価900円→500円!、リフト1日券700円割引!
☆
ようこそ!! COMPE 104 おやじのブログへ。
☆
第六回目のLessonは『山に残る切り替えと上抜け切り替えを克服』です。
山周りのエッジングを長く引きずり体が山に残る、
外スキーのエッジが残ったタイミングで伸ばした切り替えと
スキーの反応をダイレクトに受けてしまい、上に抜けてしまう切り替えを見かけます。
切り替え後、谷周りの導入期で早い捉え安定した舵取りをするのは、
山に残る切り替えと上抜け切り替えを克服しなければなりません。
☆
山に残る切り替えの原因は
①山周りは角付けが強く内側に倒れすぎ
②山周りのエッジングを引きずって長くなる
③外スキーインエッジが外れないため体の重心が谷へ移動できない
④内倒しているか?目線が内スキーより山側にある
⑤山周りのエッジングで内脚が曲がる、もしくは外脚が伸びる
☆
上抜け切り替えの原因は
①ストレッチの切り替えのイメージが強い&伸ばすタイミングが違う
②外スキーインエッジが外れないうちにストレッチし切り替える
③外スキーが外れないうちに次の外足で切り替える(シュテム操作)
④足首が緩み、膝・股関節が伸びてしまう
⑤外スキーの撓みを開放する方向が上、上手く脚が使えない
☆
山に残る切り替えと上抜け切り替えを克服して
スムーズな切り替えと推進する切り替え、そして谷周りの早い段階から捉えるエッジングを身に付け、
ターンの質が高く丸いターン弧を創れるスキー技術と運動を身に付けましょう(^^♪
☆
では、山に残る切り替えを直すバリエーショントレーニングを紹介します。
1)斜滑降からトップを落とす(中急斜面)
・右外足、両スキー荷重の斜滑降から右外足に重心移動するとエッジが外れる
・右外足、両スキー荷重の斜滑降から谷方向に目線を変えると重心が移動しエッジが外れる
*重心を谷移動(外スキーの上)するとエッジが外れ山側に残らないことを習得できる
2)山周り2段エッジング
・山周りの舵取り中、エッジを強くエッジを弱くする2弾エッジングで滑走
・強くするとトップは山へ、弱くすると斜滑降に(同時に谷へ重心が移動)なる
・フォールライン過ぎまでは強いエッジング、徐々にエッジングを外しながら重心移動を意識
*エッジングの強弱で谷への移動が可能になる
3)山周りで外側の軸を緩める
・外スキーにかかる圧に対して、徐々に圧を緩める
・足首は緊張するが、膝・股関節は幾分緩み脚が屈曲する
・脚の幾分の屈曲で重心が外スキーの上に移動できる
*山側に残る切り替えを直すのは、『谷方向への重心移動』がカギの様です。
そのポイントはエッジを緩める、
緩めるには外スキーの圧を脚・股関節を柔軟に使い緩める事です。
☆
『上抜け切り替え』を直すには『山に残る切り替え』を克服が前提です。
では、上抜けの切り替えを直すバリエーショントレーニングを紹介します。
1)三関節の曲がりを保持したまま切り替え
・足首を緊張し、三関節の柔軟性を保ちながら切り替える
・足首を緊張し、股関節に両手を当てながら連続ターン
2)横滑りから斜滑降(中・急斜面)
・右外足、横滑り(右外足に重心移動した状態)から斜滑降することでトップが落ちる
・外スキーから内スキーに入れ替わるタイミングを知る
3)グリュニゲンターンで内主導の切り替えを習得
・外スキー片足で切り替え内スキーに変わることでスムーズな切り替えに
・内スキーに変わることで上に抜けない
・内スキーに変わることで踏みかえシュテム操作が出ない
4)外スキーを踏むタイミングを知る
・外スキーのエッジが外れ雪面とフラッになったニュートラル過ぎに踏む
・シュテム操作がなくなりスムーズな切り替えと上抜けがなくなる
*内主導の時代ではありませんがグリュニゲンターンが出来ることで、
内スキーの荷重バランスの習得と同時に、外スキーの踏むタイミングも習得できます。
☆
『山に残る切り替え』と『上抜け切り替え』を克服出来るだけではなく、
山周りの仕上げの運動と谷周り始動期の運動が習得でき、ターン全体のバランスが良くなります。
☆
今回は上達の過程でかなり重要なポイントになりますので、このバリエーショントレーニングを実践し、
『山に残る切り替え』と『上抜け切り替え』を克服を克服してください。
☆
次回は、『Lesson.7 大回りズレズレターンを克服』です。
お楽しみに(^^♪