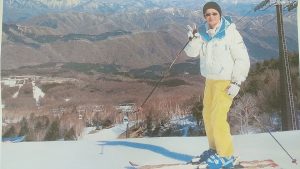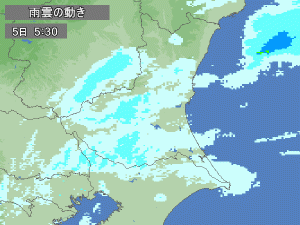今朝も寒い朝でした!
ラスカでは先週ちびっこ野球、今日はちびっこサッカーの大会が有るようですね?!
朝トレーニングに出掛けるのが遅く
いつものラスカ総合運動公園の頂上鐘の丘に着く頃は陽が上がって
日光連山を望むことは出来ないので雪が降ってるようですね!
今日OPENした尾瀬岩鞍と
茨城県スキー連盟の指導員研修会が丸沼で開催しています。
やっと、本格的に冬モードになってきて嬉しい感じです(‘ω’)ノ
☆
ようこそ!! COMPE 104 おやじのブログヘ。
☆
12日の定休日はやっぱりホームのハンターに!
全日の夕方からの降雪で上越の様な重い雪が15cm程積もり、
でも、朝一の頂上は小雨( ;∀;)
唯一オープンしているウォールストリートでは圧雪車が入ってくれたので良かった!
平日仲間はご覧の皆さん
☆
圧雪された綺麗なバーンは30分と持たなかった!
一気にもっさもさの荒れたバーン状況でロングターン
・安定しない外スキーとズレ
・内倒を誘引してしまう方のラインと目線
・重心移動をいしきする山周り等々、課題が満載!!
外スキー踏みつけラインにしっかり乗って、ソール面に壁を作る意識が重要
なので、
内スキーをちょいリフト気味に乗ってみるとズレの少ないターンが習得できる
ポイントは、
・肩のラインを平行にする
・外スキーインエッジには外腰で乗る
・ただ上げるのではなく、内スキーのエッジを外脚に反り上げる(内反させる)
*外力と自重が外スキーに集中することで外スキーが撓みスキーが走る
☆
午前中ラストのロングターン
しっかり外スキーで乗れるポジショニングには足首の緊張と水平を意識した方のラインは必須!
来週からロング用でロングターンしたいですね(‘ω’)ノ
お昼頃から天気は回復!
朝の小雨が嘘のよう!こんなにいい天気に!!
☆
1)午後はお腹いっぱいだけどショートターン
・上体のローテーションと、ローテーションを生じてしまうストックワーク
・エッジングの力でスピードコントロールが止めの操作に
・山に残る切り替えなど課題は山積み!!
☆
手が下がり、リングが後ろに流されてローテ―ションで上体が山に残るので
2)両手を高く幅広く意識してエアーストック
*ストックワークで上体の安定したバランスを保持するのが目的
ポイントは
・両こぶしが肩の高い位置を保持
・手首を動かしてリズムを取りエアーストック
・両手を広めに構えてバランス強化
☆
3)仕上げのアンギュレーション
*スムーズな舵取りと切り替えを可能にする
ポイントは
・上体面を少し深くした角度を保持する
・上体と大腿骨の外股関節の角度を保持する
・両脚の回旋(内脚の外旋主体)で山周りの仕上げる
*アンギュレーション(逆捻り)の状態からスムーズな切り替えが可能になる
☆
4)ストックの付く(置く)タイミングと位置
*走る切り替えと上体とスキーのスムーズなクロスオーバーが可能になる
突く(置く)タイミングのポイントは
・ニュウートラルからエッジが効き始まるタイミング
・そる部分が見えないタイミングで
*タイミングを習得できる事で止めのエッジングから走るエッジングに
突く(置く)位置ののポイントは
・スキーに対して直角方向でブーツ真横の遠くを意識
・遠くを意識することで上体が谷に移動しやすい
*タイミングと付く位置が調和すると、
スムーズな切り替えと見せ場の谷周りが大きくなり深周りが出来る
☆
硬く荒れたバーン、強風に中で最後の小回り
幾分、丁寧な操作のためかターンサイズが大きくなっていますが、
切り替えと舵取りがスムーズになるためのストックワークとアンギュレーションが
少しずつですが改善されていると思われます。
☆
来週はマジソンとニューマジソンがOPENして
ロングターンのスキーでロングを新しいウェアで練習をしたいと思っています(‘ω’)ノ